オンライン資格確認とは、医療機関や薬局で2021年3月から実施予定の新たな制度です。(2021年1月現在)
オンライン資格確認では、マイナンバーカードのICチップを利用し、保険証入力の手間が省略できるなど、窓口業務を6~8割削減できると言われています。
業務が削減されるのは嬉しいですが、そのために準備は必要となります。
その1つが富士通を含めた3社から申し込みできる、顔認証付きカードリーダーです。
富士通では、2020年7月から、オンライン資格確認についてセミナーを通じて発信していました。
そこで、オンライン資格確認、富士通の顔認証付きカードリーダー、オンライン資格確認のデメリットについても調べてみました。
オンライン資格確認は富士通のカードリーダーで!?

オンライン資格確認とはどういう内容か確認し、富士通が提供する顔認証付きカードリーダーや、必要なシステムについても見ていきましょう。
オンライン資格確認とは
オンライン資格確認について、再度確認しておきます。
今まで、医療機関のシステムに保険証記号番号などを入力していましたが、マイナンバーカードのICチップを利用すれば、自動的に取り込むことができるようになります。
健康保険証でも、もちろん可能ですので安心してください。
健康保険証の場合、最低限入力する必要はありますが、マイナンバーカード利用時と同じように、資格情報を取り込むことができます。
オンライン資格確認ができることによるメリットとしてよくあげられるのは下記の3点です。
- 保険証記号番号など、入力の手間が省略できる
- 資格の確認が即座にできるため、失効している保険証での受診がなくなる
- 予約されている方の情報を来院・来局前に確認できる
さらに、災害時の特別措置として、薬剤情報の閲覧が可能となります。
閲覧が可能になることで、どこにいても必要かつ適切な医療を提供することが可能になります。
受診側としても、避難所などで薬が欲しい場合もすぐ手に入れることができるのは心強いですね。
あくまで災害時の特別措置ですので、通常は本人がマイナンバーカードで本人確認し、同意した場合のみに限ります。
富士通のCaoraについて
顔認証付きカードリーダーは富士通、パナソニック、アルメックスの製品から選ぶことができます。
今回は、富士通の製品について少し調べてみました。
富士通Japan株式会社では「Caora」という顔認証付きカードリーダーを提供予定となっています。(2021年1月現在)
Caoraの特徴についてまとめましたので、参考にしてください。
- 眼鏡やマスクに対応したAI技術搭載
- 1台のパソコンに4台までCaoraを設置可能
- 様々な背の高さの方に対応している広角レンズ搭載
- 軽いタッチで操作可能な静電容量方式タッチパネル搭載
- のぞき見防止フィルター添付
- 5年間の保守費用が含まれているため、故障時も安心
簡単にあげただけでも、6つの特徴があるのは素晴らしいですね。
もっと詳細が知りたい、富士通以外の2社についても知りたい、という場合、後で紹介するポータルサイトで詳細が確認できます。
顔認証付きカードリーダー以外にも、オンライン資格確認用のパソコン、レセプトコンピュータの改修等などが必要となります。
オンライン資格確認の導入にはポータルサイト登録から

オンライン資格確認の導入を検討している場合、まずは医療機関等向けポータルサイトに登録する必要があります。
ポータルサイトに登録すると、そこから補助金の申請ができ、今後メールやお知らせなどが届きます。
先ほどご紹介した、オンライン資格確認に必要な顔認証付きカードリーダーの申し込みも、ポータルサイトから可能です。
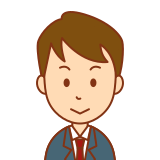
オンライン資格確認を導入しようと思ったら、ポータルサイトへの登録が必須ってことなんだな。
登録は必須ではありませんが、「申請した方が便利だよ、色んな申請がここからできるよ。」というような内容が書かれています。
登録方法はとてもわかりやすく、2ステップで可能です。
- メールアドレスを入力し、仮登録メールを送信する。
- 送られてきたメールに記載のURLにて登録手続きを行う。
ちなみに、1ヶ所の医療機関で登録できるアドレスは1つのみのようです。
オンライン資格確認のデメリットとは

ここから、オンライン資格確認のデメリットについても調べていきたいと思います。
オンライン資格確認をすることによって、気になる点を3つあげてみます。
- セキュリティ面
- 端末故障時等の維持費
- 最初に患者側の手続きが必要
どういうことか、それぞれ詳しく見ていきましょう。
セキュリティ
マイナンバーカード自体にまだ馴染みのない私自身も、セキュリティは大丈夫なのだろうかと一番気になるところです。
マイナンバーカードの取り扱いとなると、保険証以上にセキュリティの管理が必要とされます。
資格確認のために、インターネット回線が必須となりますのでウイルス対策も併せて必要となります。
維持費は医療機関側が負担
補助金を利用して、初期費用がかからなくても、端末故障時の修理費は医療機関側の負担となります。
当然ながら、先ほどの懸念点であるセキュリティ対策も、医療機関側の費用となります。
今までかかっていなかった費用がかかる。というのは結構大きな問題ではないでしょうか。
最初に患者側の手続きが必要
私が初めてオンライン資格確認について調べたとき、「マイナンバーカードのICチップを利用するだけならとても便利だな」と思いました。
しかし、利用するためにはあらかじめ手続きが必要となります。

複雑な方法だとできないな…。
どのような手続きが必要なのか、下記を参考にしてください。
- マイナポータルサイト内の保険証利用申し込みページにアクセス
- マイナンバーカード受け取り時に設定した4桁の暗証番号を入力
- マイナンバーカードを読み込み
登録の手続き自体は複雑ではありませんが、全ての人ができるかは疑問ですね。
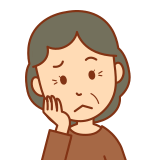
パソコンやスマートフォンの操作が得意ではないのだけれど…。
実際に、厚生労働省のホームページ内に「利用申込サポート実施へのご協力をお願いします」という文言とともに、ガイドブックが掲載されています。
つまり、医療機関や薬局でも登録のサポートしてね。ということなんですよね。
ちなみに、医療機関や薬局では、顔認証付きカードリーダーでも登録ができるようです。
登録のサポートが必要となりますので、窓口が混み合うのではないか、という指摘もあります。
まとめ

- オンライン資格確認とは、医療機関や薬局でマイナンバーカードを用いてオンラインで資格確認をすること
- オンライン資格確認には富士通などが提供する顔認証付きカードリーダーが必要
- 富士通の顔認証付きカードリーダー「Caora」は眼鏡やマスクにも対応のAI技術搭載などの特徴がある
- オンライン資格確認にはポータルサイトの登録がおすすめ
- オンライン資格確認導入の際は、セキュリティ面について慎重な選定が必要
- オンライン資格確認を患者が利用する際、初期登録が必須
オンライン資格確認について、富士通の「Caora」など必要な機器についても調べてみました。
オンライン資格確認の導入は必ずしも必須というわけではありませんが、検討する場合はさまざまな角度から考慮する必要がありそうですね。

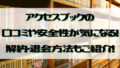

コメント