 生活全般
生活全般 出張が多い彼氏との上手い付き合い方は!?寂しい気持ちの伝え方や将来についても!
出張の多い彼氏に、感情的に寂しさをぶつけてしまうと、彼氏は仕事の疲れプラスメンタルも攻撃してしまう事になります。
出張の多い彼氏に、会いたいときに会えない事や不安に感じていることを伝えると、重荷になってしまうと不安になりませんか?
...
 生活全般
生活全般 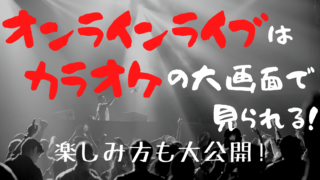 生活全般
生活全般  生活全般
生活全般 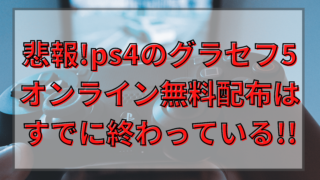 ゲーム・家電
ゲーム・家電 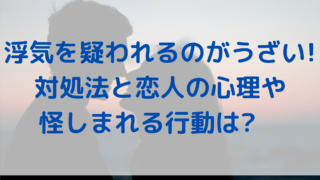 生活全般
生活全般 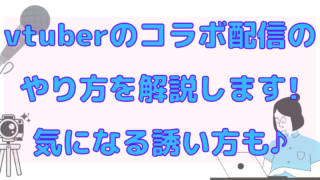 動画配信系
動画配信系  生活全般
生活全般 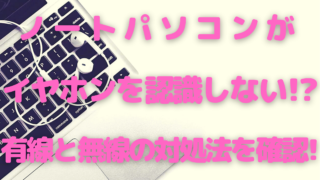 ゲーム・家電
ゲーム・家電 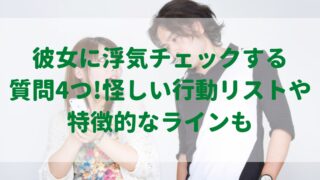 生活全般
生活全般 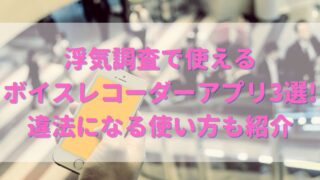 生活全般
生活全般