 生活全般
生活全般 叙々苑コースのメニューと値段を徹底調査!雅と彩の違いや単品注文との比較も!
誰もが憧れる高級焼き肉店の「叙々苑」。普段の食事ではなかなか行けなくても、特別な日には少し奮発して叙々苑で食事を楽しみたいですよね。
しかし、叙々苑の公式サイトを見ても、掲載されているのはコース名と金額だけ。
しかも店舗によっ...
 生活全般
生活全般 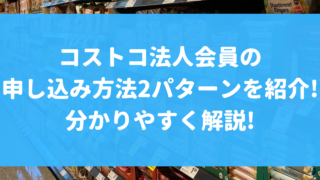 生活全般
生活全般  生活全般
生活全般 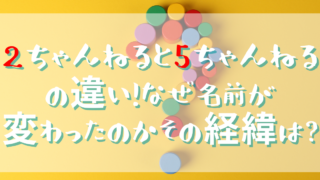 生活全般
生活全般 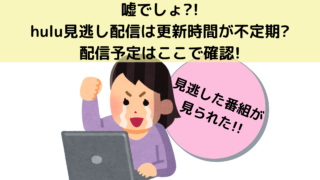 動画配信系
動画配信系  生活全般
生活全般 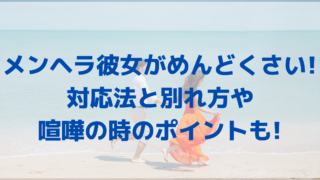 生活全般
生活全般 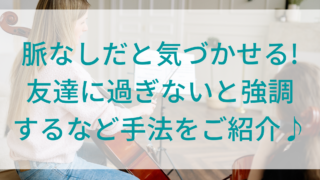 生活全般
生活全般 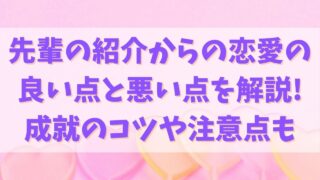 生活全般
生活全般 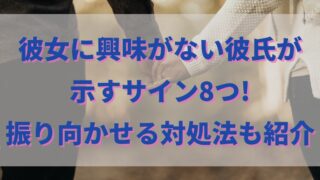 生活全般
生活全般